旅の楽しみ方 IN ネパール
 初めての一眼レフカメラの失敗
初めての一眼レフカメラの失敗
もう8年ほどデジタルカメラを使っていましたが、気に入っていた一台めが落として壊れてしまい、
2台めのコンパクトカメラは、液晶画面が晴天の日だとまぶしすぎて買ってすぐに気に入らず。
そしてネパールの旅に行く前の、一週間ほど前になって 夫の薦めで
ようやく決心をして一眼レフカメラを買いました。
押すだけで 、ほとんど説明書も見ないまま現地に。
海外では、コンセントの形体が違うので、現地に合うプラグを買いました。
初めて、充電しようと思ったら、停電。ネパールでは、しょっちゅう停電で、朝8時から夕方4時まで
は停電ということがほとんど。
そんな訳で、やっと電気がきたとほっとして、コンセントに差し込んだものの 充電のランプがつかない。
えっ、えっ、そんなこと、、、と どっきり。
プラグを差し込んだところは、まとめて5箇所ほどコンセントが差し込むようになっているコード
再び、壁に直接コンセントが出ているところに プラグを差し込んだところ
やっとで 充電のスイッチが点灯して ほっと しました。
しかし 大型家電で購入時に聞いた、デジカメのチップにで何枚取れるか
聞いてメモリーを買ったのですが
現地で撮っている途中で メモリーが少なくなってまるという 警告ランプが、、、
余分なメモリーはもってなかったので、あせって 同じような写真を消すという作業
それも 停電のなか ろうそくの 灯りがともるなかで の作業になってしましました。
(高かったけれど予備の 充電器を買ってもってきてよかったです)
それでも 最後の2.3日には もうMサイズからSサイズに画像解像度を落として 撮ることにしました
(日本出発前に 不安になって知人に聞いたことから 余分にメモリーを持ってくるべきだった)
そして日本に帰国し、現像してみると、思ったより写真が暗く、画像の粒子が荒れていて ショック。
気になって、カメラの解説書をみて 原因を追求してみると
なんと いつの間にか、露出のボタンが動いていて
その暗いままで 撮っていたのが原因らしいのです
そんな訳で、今回の写真は絶望感を抱いていたのですが
先週いった 美容院の方が、「ネパールの写真出来たら、また見せてください」
と言ってもらえたので 少しずつ まとめている この頃です
プロじゃないんだから 雰囲気だけ伝わればいいじゃないか、、と思えてきました。
旅先には やはり慣れたカメラが一番です
それでも 写真をまとめていると それなりに 「いいじゃないか・・」なんて嬉しくなってきて、、
13年程前の「ネパールのこども達」の写真と合わせたら
小さな 小さな 個展が出来るんじゃないかと あきらめていた夢が膨らんできたりして
(ネパールで出来たカレンダーを売るための
小道具的なな写真であり、個展をやるほどまでの 写真でなくともよいのですが)
旅のまとめは、あまり熱が冷めないうちに まとめていくと
次の行動に移りたくなり なにか小さな扉が開きそうな予感がしてます。
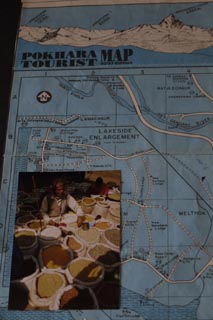








 、
、

